GRADE第2版に関連した、MLをスタートさせています。
オリジナルのGRADEシステムを理解し、さらにGRADEの適用拡大について解説していきたいと思います。
参加希望者は、直接連絡ください。
GRADEアプローチは、EBMを理解しようとする方、システマティックレビューの著者や診療ガイドラインや医療技術評価(HTA)における推奨を作成する方々などを対象としています。GRADE適用の具体的なものとしては、治療に関するGRADE、診断に関するGRADEなどさまざまなものがありますが、あくまで基本は、”治療GRADE”です。
ところで、GRADE working groupは、今後、GRADEシステムをどのような方向にしたいと考えているのでしょうか。
一つは、DECIDEと連携した Evidence to Decision framworkの確立で、もう一つは、MAGICと連携した信頼できるガイドラインの作成と普及・利用です。
EBMにおけるGRADEの適用という視点では、治療研究におけるGRADE、診断研究におけるGRADE、~~~などといった方向であり、つまり、EBM Working groupが作成した「JAMA Users’ Guides to the Medical Literature」の内容に合わせて、GRADEアプローチを開発しています。
●予後研究におけるGRADE:
Judging the quality of evidence in reviews of prognostic factor research:adapting the GRADE framework. Systematic Reviews 2013, 2:71
●予後に関するエビデンスのユーザーズガイド
上記の「医学文献ユーザーズガイド 根拠に基づく診療のマニュアル(第2版)」の第18章を参照。
予後に関するユーザーズガイドも参照していただきたい。
「JAMA Users’ Guides to Medical Literature」を翻訳した「医学文献ユーザーズガイド 根拠に基づく診療のマニュアル(第2版)」(相原、凸版メディア, 2010)の”上級編”にはGRADEシステムの基本が記載されています。
UpToDateに示されるエビデンスの質や推奨の強さの意味を理解するためにも、ぜひGRADEの基本をマスターしてほしいと思います。
UpToDateの Medical Calculators
http://www.uptodate.com/home/medical-calculators
UpToDateにおいて提示されているエビデンスの質や推奨の強さは、GRADEシステムを使ったものです。
GRADEシステムを使った日本発のシステマティック・レビューです。
Recombinant human soluble thrombomodulin in severe sepsis: a systematic review and meta-analysis.
Yamakawa K, Aihara M, Ogura H, Yuhara H, Hamasaki T, Shimazu T.
J Thromb Haemost. 2015 Jan 10. doi: 10.1111/jth.12841. [Epub ahead of print]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25581687
提示しているエビデンステーブルは、Evidence profileではなく、SoFです。
GRADEにおいては、”エビデンスの質”、”エビデンスの確信性”、”エビデンスのレベル”、”エビデンスの強さ”、”エビデンスの等級”、”効果推定値の確信性”などの用語が登場しますが、すべて同じものです。
どのように使い分けしているのかというと、以下と思います。
| ●GRADE working groupの多くは、「エビデンスの質」、「効果推定値の確信性」を使っている(これは、JCE GRADEシリーズから明白です)。 |
| ●DECIDE groupは、「エビデンスの確信性」、「エビデンスの質」を使っている(GRADE handbookやEvidence to Decisionテーブルなどから明白です)。 |
| ●EBM guideline(GRADEシステムを利用:フィンランド)においては、「エビデンスの質」、「エビデンスのレベル」を使っている(右リンクを参照http://www.grade-jpn.com/evid_statement.html) |
| ●Cochrane groupは、「エビデンスの質」を使っている(Cochrane handbook)。 |
診療ガイドラインやシステマティック・レビューのための国際的スタンダードである「GRADEシステム」とは、どのように使うのか・・・・・・・
GRADE教科書改訂版である第2版(「診療ガイドラインのためのGRADEシステム 第2版」2015年春出版予定)に関するディスカッションのために、以下のML(2015年スタート)を、新規に立ち上げました。
http://www.freeml.com/grade-jp
参加希望者は、直接 ezy01757@nifty.ne.jp へ連絡ください。
”GRADEシステムの基本が実はこれほど単純だった”ということが理解できると思います。GRADEに関する初歩的な疑問から解決していきましょう。
もう十分にGRADEを理解しているという方も、これからGRADEを新たに理解したいと思うからも、さらには、GRADEをさらに高度に活用したい(診断や予後、間接比較やネットワークメタアナリシスなど)と思う方々もどうぞ!!
*GRADEを”改変”して利用したいと思っている方は、ご遠慮ください。
*エビデンスの質評価において「非GRADE」を利用している方々には、全く参考にならない情報ばかりですので遠慮ください。
GRADEシステム以外は不適切というつもりは全くないです
日本医療機能評価機構 医療情報サービス(Minds)は、厚労省の委託事業である。つまり、我々の税金を使って実施している事業ということになる。
そのMindsは、コクランのCDSR抄録の翻訳も(版権取得して)実施している。
当然ならば、コクランレビューにおけるエビデンスの質評価は、GRADEシステムを利用したものである。
一部のレビューには、「推奨」さえも記載されているものもある。
Mindsが「コクラン」を重視すればするほど、GRADEシステムを認めざるを得ない。
でもって、ガイドライン作成においては、Minds2014ではなく、GRADEに従わざるを得ない。
これは、(GRADEを改変した独自の基準を発表したMindsにとっては)相当なジレンマであろう。
ましてや、いまでもMinds2007を公開しており。だれでもが閲覧・利用できる・・・・ (–;
Minds2007は一見単純で便利そうだが、まったく不適切極まりないもので、GRADEシステムとは相反する基準である。
まずは、この事実を Minds自ら認めて、
●「Minds2007を利用すべきはない」
●「Minds2007を使った診療ガイドラインは早急に改訂すべき」
と公示すべきでしょう。
そうしないと、国内の診療ガイドラインの質は向上しない。
Minds主催の「GRADEを理解するためのワークショップ」は、もう、十分な回数を実施したはずである。
GRADEシステムをよく理解できない、と思う方は
GRADEシステムを参考にしてほしい。
英語が得意ならば・・・
Go to http://www.gradeworkinggroup.org/index.htm
You can find a lot of information in the publication section, or, if unsuccessful, send us an email with your question: mail@gradeworkinggroup.org
CPGへの影響力を考えると、診療ガイドラインの手引きを作成したり、国内の診療ガイドラインにお墨付きを与えている日本医療機能評価機構のMindsが変わらないといけない。
CPGを使う側がいかにGRADEシステムを適切に理解しても、CPGを作る側が不適切なGRADEを使っていては・・・
患者にとって重要なアウトカム(patient-important outcomes)は改善しない。
Minds関係者だけではなく診療ガイドラインを作成する方々は、以下の2つの違いをよく理解すべきです。
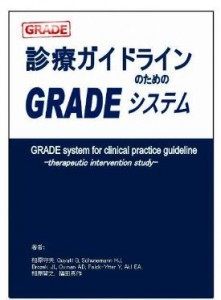
|

|
GuyattやSchunemannが何度も述べているように、不適切なGRADEの改変はよくないし、混乱を招くだけです。
「診療ガイドラインのためのGRADEシステム」 に記載されているGordon Guyattの序文を読んでほしい。
「Mindsの提案する診療ガイドライン作成方法」が公開された。
http://minds4.jcqhc.or.jp/seminar/12/pdf/3_Yoshida_20141018.pdf
これって、・・・・ 「GRADEに準拠している」と述べる必要があるだろう!
Mindsグループが 独自に考案したグレードダウンとグレードアップというアプローチならば、その根拠を明示しなくてはならない。
よくも大胆に発表できるものだと思うが・・・・
Don’t “mind” ということか
当該発表者は他の学会では、”ガイドライン作成におけるGRADE利用”を明言している以上、このような誤解を受けるようなことをしてはいけない。
このことはとても重要なことであることを、Mindsグループは認識する必要がある。
いずれにしても、教授がこのような発表をしては、若手に示しがつかない。
(現状におけるCPG乱造をみると)国内においては、どのような質であっても、診療ガイドラインと名のつくものを作成したいという流れがあると思う。
パネルや編集者の業績になることもあるでしょうし、製薬会社の要望もあるでしょうし、他の学会が実施しているのでわれわれもという流れもあるでしょう、・・・・ でも、結局は、患者にとっての重要なアウトカムはおろそかになっていると思います。
血圧が3mmHg低下、HbA1Cが0.5%低下、・・・・癌検診における発見率・・・
多くの国内の診療ガイドラインを見るにつけ、よくも合意形成ができているものだと驚くばかりです。議長のスキルがすぐれているのでしょう。
どのように合意が形成されているのか、さっぱりわからないものが殆どです。
COIについても、「本件についてはCOIはない」と決まり文句を記載すればよいというものではないです。
作成した診療ガイドラインが、どのようなIOMやAGREE-2評価だったのかを、開示してほしいです。
GRADEを使ったならば、GRADEシステムを利用したと言えるための最低限の基準をチェックしてほしいです。
そして、各項目がどのように評価されるかを、考えてみてください。