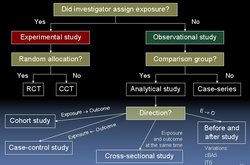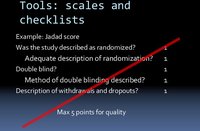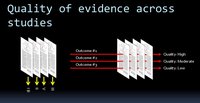GRADEシステムは、エビデンスの質と、推奨度の評価を分離していますが、
エビデンスのまとめの提示や、ガイドライン作成における「GRADEシステムの位置づけ」を理解しておく必要があります。
今後、このリンクサイトにもいくつかのGRADE関連資料を公開していきたいと思っています。
(引用は自由ですが、当webサイトからの出典であることを明らかにしてください。)
本資料サイトにおいて、エビデンスプロファイルやコクランSoFテーブルなどの基本的なフォーマットも紹介しますが、(GRADEエビデンステーブルにおける最低限必要な記載項目はあるものの)サンプル例と同一にする必要性はないので誤解されないようお願いします。
また、私のHP、および関連サイト内容のうち、古い情報については改変修正している余裕はないので、常に最新情報を海外GRADE working groupが発表する英文論文などで確認してください。