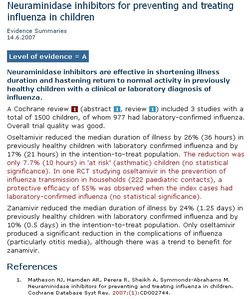■インフルエンザ患者のタミフル処方頻度は、厚生労働研究班の発表から推測できます。平成17年報告(横田;インフルエンザに伴う随伴症状の発現状況に関する調査研究)ではタミフル処方は90%で、平成19年では(約1万人)78%です。タミフルと、いわゆる異常行動との関連調査では、非投与群では12%、タミフル投与群では16%ですが、この両者のデータを単順に比較することは好ましくなく、実際の臨床で主治医がどのようにして患者を登録したかを想像するとすぐに理解できます。
■本研究班の調査においては、単にインフルエンザと迅速検査で診断した患者について、(調査の同意を得て)、診療します。そして、タミフル処方、非処方にかかわらず、観察しています。
————————————————————-
・ある患者は、来院当日の朝に高熱があったものの受診時には解熱して元気だがインフルエンザ検査が陽性だった。→ 主治医の対応は、タミフル非投与で観察。
・別の患者は、来院受診時に発熱があって、検査で陽性であったが、主治医はタミフル処方をせず、観察した。
・さらに3例目は、発熱は一時的で、検査が陽性であり、親の希望で、タミフルを処方した。
・4例目は、高熱があり来院、検査が陽性で、主治医はリレンザを処方した。
—————————————————————–
このようにして、連続して10例~20例を登録するということで、研究デザインとしては多くのバイアス因子があり、全くランダム割付とはいえないものです。この結果からは、単に頻度だけしか知りえないし、信頼区間を推定しても、そのデータのみから得られるものであり、例数が増えると、信頼区間が狭くなるというだけの話と思います。
2000人を、あるいは1万人を、年月にわたって観察するという研究とは違います。しかも、我々が知りたいのは、特に投薬1~2日以内の異常行動の差です。
従って、世界中で日本が一番タミフルを処方している国である以上は、処方することが非倫理的と言われることはないでしょうし、両者の差から、サンプルサイズを算出して、ランダム化比較試験を実施することが一番早道と思いますが、研究班では今後はこれまでの蓄積された例で解析するという方針のようです。
α=0.05, β=0.8として、各群1500人弱のもので比較できるものを、どうして計画しないのか理解ができません。ランダム化試験は非倫理的という方もいますが、それでは、研究班調査で報告された8000人近くの患者が非倫理的な医療を受けたことになってしいます。今後も研究班が継続するケースシリーズという very low levelの研究デザインの膨大な結果を、後付でいろいろと処理しても、得られるのデータは信頼性が低いものに変わりないと思われます。
ちなみに、当院での10数例での連続した観察では、タミフル処方では異常行動はなく、非投与で1例、リレンザで1例観察された。リレンザ例では、1回使用後です。
Cochrane レビューを利用したEBM-Guidelineでは、どのような評価(GRADE分類)になっているのかというと、図のような判定です(CDSR 2007)。
また、小児・成人全体での報告もあり経済評価も記載されていますが、ここでは省略します。
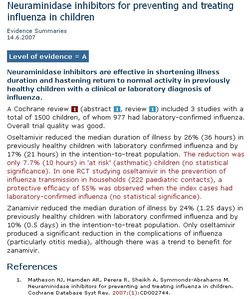
私見としてまとめると、
(1) インフルエンザ患者に対してのタミフル投与は、投与時期が早期の場合に限って、発熱期間を1日程度短縮するだけであり、わずかな効果にすぎない。
(2) 健康成人の通常の(非パンデミック)インフルエンザには、治療・予防でも適応ではない。
(3) タミフル投与すると、嘔吐が小児・成人患者で多い(第1~2病日)。従って、タミフルの投薬(薬剤だけの価格4300円を考慮しても)は、メリットにみあったものではないだろう。
(4) タミフルと中枢神経有害事象はこれまでの質の高い研究からは、関連性が明らかでない。
(5)国内外の試験では、タミフル耐性ウイルスの出現が、小児で約4%。
(6)日本から特に報告が多い、神経精神異常という有害事象は、別のデザインで調査すべきであり、このままでは、同じような第1~2日以内の高発症率データを、かってに解釈して論争がつづくだけである。イベントの発症率からあえて、症例対照研究を考える必要性は全くないだろう。