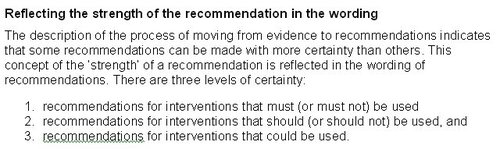治療関連の報告論文をみて、その結果を自分の目の前の患者に適用できるかどうかの評価のひとつに、生物学的要因(biologic factors)が治療効果に影響を及ぼすかどうかを考える必要があります。
その場合の、おぼえやすい指標が、SCRAP (*)であり、性別(Sex), 併存症(Comorbidity), 人種(Race), 年齢(Age), 病理(Pathology)の略です。
——————————————————-
● Sex: アテローム硬化症予防のアスピリン有効性:脳心血管障害の相対的リスク減少は、男性よりも女性で大きい。
● Comorbidities: 高血圧治療: 拡張期血圧の目標を80mmHg以下とすることは、糖尿病患者ではイベント減少につながるが、全体ではそのようなことはない。
● Race: 高血圧の利尿剤は白人よりも黒人で反応がよく、消化性潰瘍のPPI治療はアジア人のほうがそうでない人種よりも効果的。
● Age: インフルエンザワクチンによる予防は、高齢者で免疫反応が低く、消化性潰瘍の2剤治療は、高齢者ではピロリ菌除菌効果がより高い。
● Pathology: インフルエンザ予防のためのインフルエンザワクチンの有効性は、使用ウイルス株に依存している。乳癌化学療法の反応性は、ある種の遺伝子発現に依存している。
——————————————————-
[コメント]
このような因子については、システマテイックレビューなどでもサブ解析として検討されますが、GRADEシステムにおいては、indirectness、inconsistency (heterogeneity) のチェックに役立つものです。
(*) JAMA Users’ guides to the Medical Literature 2e(11.1章)にも記載されている内容です。
: