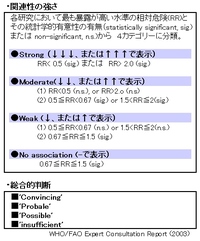以前、アバスチン(bevacizumab)の抗がん剤としての benefits、riskについて記載しましたが、今回は眼科領域での使用についてです。
血管内皮増殖因子(VEGF)に対するモノクロ抗体が、もとは悪性腫瘍に対する分子治療として登場したものの、網膜疾患で、眼内注射として使用され、劇的な効果があるようだということです。
—————————————————————
■なぜ効果があるのか?
例えば糖尿病性網膜症では、虚血網膜からVEGFが産生されて、眼内に新生血管が発生し、その新生血管が破綻して出血が起こる。また、失明につながる加齢黄斑変性の新生血管の発生にも、この因子が関与していて、VEGFを眼内で直接抑制する薬剤が期待されていた。
2005年に、マイアミ大学でVEGFモノクロ抗体を数人の患者に試したところ、劇的な効果があった。
■どの程度で効果があるのか?
投与数日から1週間程度で、効果があり、また非常に安価である、ということが普及の理由のようである。しかも、眼内注射の投与量はわずかに 1.25mg/0.05mlというもので、抗がん剤として発売されている1バイアル(400mg/16ml)を小分けにすると、1回の費用は数千円ということである。
■安全なのか?
有害な副作用はわずか0.2%程度という報告もあるが、眼内に注入された抗体は非常に低濃度でも全身に循環するようで、脳梗塞などの血管閉塞性疾患の確率が高くなるのではという意見もある。
また、治療の問題点として、数ヶ月後に再発が多いようだということと、保険適応外ということである。
■現時点での報告は?
“central retinal artery occlusion”,”bevacizumab”で検索すると、
(1)PubMed: 3件(2件の症例報告と、1件のmulticenter studyがありこちらは12カ国70施設で約 5000人)
(2)国内論文の検索では、殆どヒットせず、医中誌で1件、JSTAGEで0、メデイカルオンラインで1件のみです(眼科関連では)。
*参考: 近藤峰生(名古屋大学)、日本医師会雑誌 2007; 136: 1558
—————————————————————
Wall Street Journal(WSJ)の報道によると、”世界で2番目に大きなバイオテクノロジー企業・Genentech社は、癌治療薬・アバスチン(Avastin;ベバシズマブ、bevacizumab)を医師が安価な加齢黄斑変性症(AMD)治療薬として使用するのを困難にしうる計画の実行が遅れています”。
(Biotoday, 11/1)