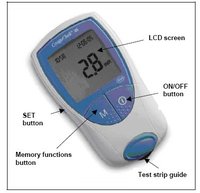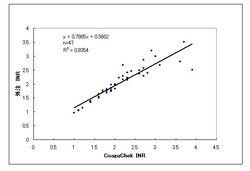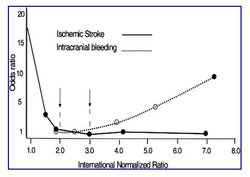GRADE システムの海外の普及については、これまで本ブログ、あるいは当院HPで何度も紹介していますが、その普及のスピードはすさまじいもので、津波のごとくです(海外論文をみる限り)。
診療領域とは関連なく、これまで推奨を表現しないとしてきた、BMJ-Clinical Evidence, NICEガイドラインのみならず、感染症領域、消化管領域での論文が次々と登場してきています。
一方、国内ではいまだGRADEの基本を遵守したガイドラインはありませんが、今後1年以内には適切なGRADEガイドラインが登場してくるように思いますし、そう願っています。
国内で認識が低いのは、日本語での GRADE紹介論文が少ないということが一番の原因と思われますが、(決して自慢ということではなく)、当院HPからのDL可能論文、および、GRADE working groupで公開しているFAQの日本語翻訳、簡略版GRADEシステム,などを参考にしてほしいと思います。
GRADEシステムに関しての、日本語発表資料は、この他にはないのか? というと、今春発表の厚生労働研究班2008の分担報告資料が一件あります。同じ著者が、消化器病学会抄録で発表していますが、全くGRADEシステムに関しては誤った認識です。当然ながら、その内容は非常に不適切なもので、当該研究班はこれが2度目の大きなミスです。本グループのGRADEに関する誤った認識に関しては海外のGRADEグループのほうには概略は伝えておきました。発表者はGRADEについて疑問があるようならば、直接Working Groupに教えてもらうべきで、不適切な理解の元での発表は迷惑というか~デメリットだけです。
GRADEシステムは、システマティックレビューやガイドラインなどにおけるエビデンスの質の評価、推奨の作成には 最も適切なアプローチですが、GRADE profiler, RevMan5などの理解も必要なため、完全理解となるとやや面倒な点はあります。
いずれにしても、昔の教科書や、EBMワークショップでの研究デザインによるエビデンスの質の評価はやめましょうということで、エビデンスの等級にはGRADEシステムを使いましょうということです。
————————————————————–
■1. 年内には、GRADEのマニュアル(タイトル未定; 日本語)を、海外メンバー(Guyatt, Schunemann, Oxman, Brozek, Akl)とともに、発表します。
■2. GRADEシステムのみならず、EBMの基本デスカッショングループ(semi-closed)を通して、EBMに関する形のあるものを発表したいと検討中です。