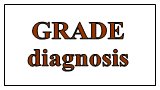エビデンスから推奨を作成するために —GRADEシステムの発展に向けて
という、GRADEシステムに関するGuyattの解説記事(インタビュア米国医療ライター Mary Mosley)が セラピューテック・リサーチ・オンラインに発表されました。
エビデンスから推奨を作成するために —GRADEシステムの発展に向けて
注:インタビュー記事の中で紹介されている、エビデンスプロファイル(EP)とSoF作成のためのフリーソフトがGRADE profiler(GRADEpro)で、GRADEproのヘルプファイルに相当するのが、GRADEハンドブックです。
・・・・・・・GRADE ハンドブック日本語版(version. 3.2)
ガイドラインを作る人や、利用する側の人は、「エビデンスと推奨を切り離して考える」というGRADEの基本(EBMの基本)を把握してほしいと思います。
GRADEワーキンググループができて、すでに10年以上経過しました。国内のすべてのガイドライン作成委員は、既報ガイドラインにおける「エビデンスの質と推奨の強さ」の評価が(国際的な標準基準である)GRADEシステムに準じているかどうか、ガイドライン作成基準を含めて再考してほしいですね。
GRADEに関して日本語で知りたいと思うかたは、以下を参照ください。
・ GRADEシステム
・ 診療ガイドラインのためのGRADEシステム
・ GRADE関連資料