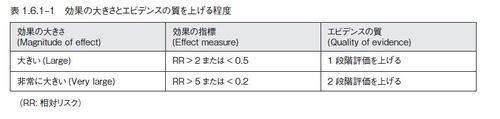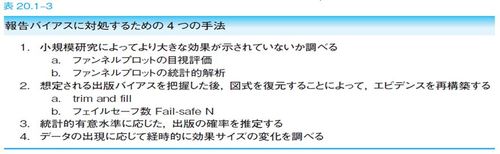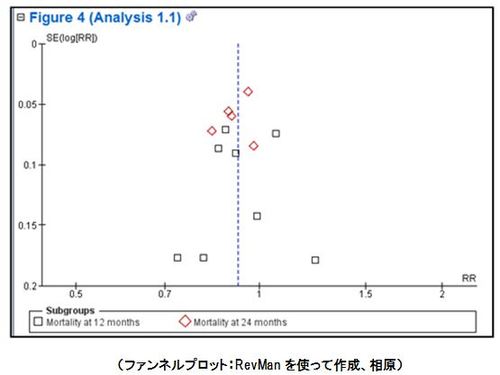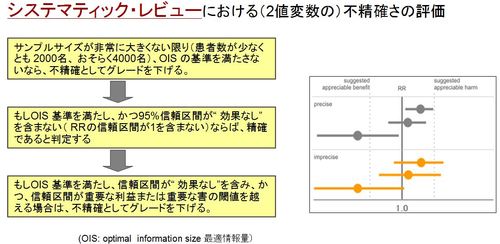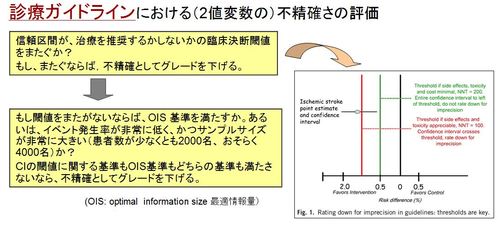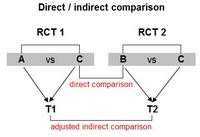複数の観察研究から得られた結果において、用量反応勾配(dose-response gradient)がある場合は、エビデンスの質を1段階上げる。ただし、評価を上げることができるのは、研究の妥当性に問題がなく、評価が下げられていない観察研究に限られる。
たとえば、1日の喫煙量の増加と肺癌による死亡リスクの増加という関連性は、喫煙が肺癌を引き起こすというエビデンスの質を上げる理由となる。
また、ワルファリンによる抗凝固療法を受けている患者において、抗凝固の程度の指標であるINR(国際標準比)の高値と出血リスク増加との間に用量反応勾配があるという観察は、治療域を超えた抗凝固レベルが出血リスクを増加させることの確信を高めるものである。
参考
用量反応勾配について(GRADEハンドブック)
シナリオにおける、2つのアウトカムに関する評価:
・全死亡率: 評価なし
・大出血: 評価なし
|
理論的にはランダム化比較試験の結果についてグレードアップすることは可能であるが説得力のある適切な報告例はなく、通常はグレードアップの3要因は観察研究を対象としたものである。 (JCE series #9: Rating up the quality of evidence) |