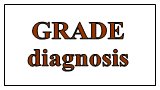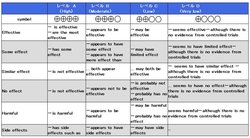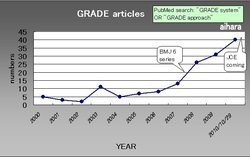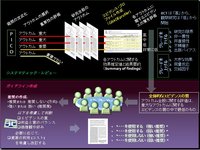アジアでは最初のGRADEセンターとなる、Chinese GRADE centerが2011年9月に、Lanzhouに設立されました。
韓国ソウル、マドリードにおけるGRADE working group会議で承認されたもので、GRADEのwebサイトでは、GRADEに関する中国語翻訳版がFAQを含めて公開されています。
以下は、GRADEのHpから:
The Chinese GRADE center is the second GRADE center in the world, and the first GRADE center in Asia. The missions of Chinese GRADE center include 1) introduce and disseminate GRADE system in China; 2) hold GRADE workshops regularly, train Chinese guideline developers and systematic reviewers and 3) translate GRADE work and GRADE software into Chinese and promote the implementation of GRADE system.
GRADEに関する日本語翻訳(FAQを含め)は??・・・・・ 以下に紹介しています。
● GRADEシステム(イントロ)
● GRADEシステムのFAQ
この、FAQ和訳は、2007年12月に、相原守夫(相原内科)、湯浅秀道(東海産業医療団中央病院歯科口腔外科)、豊島義博(第一生命日比谷診療所歯科)、斉尾武郎(フジ虎ノ門健康増進センター)が共同で実施し、2010年1月に相原守夫、三原華子(当時、国立がんセンターがん対策情報センター)、村山隆之(御殿場石川病院医療安全管理室室長)が一部を改変しました。
GRADE working groupの Yngve Falck-Ytter, Andy Oxman, Holger Schunemann, Gordon Guyattの承認を得て、2007年から公開しています。
Mindsのような国内の公的機関がGRADEシステムを採用し、GRADEの指導や普及を決定するまでは暫定的に日本語翻訳版を私のHPで紹介するつもりです。