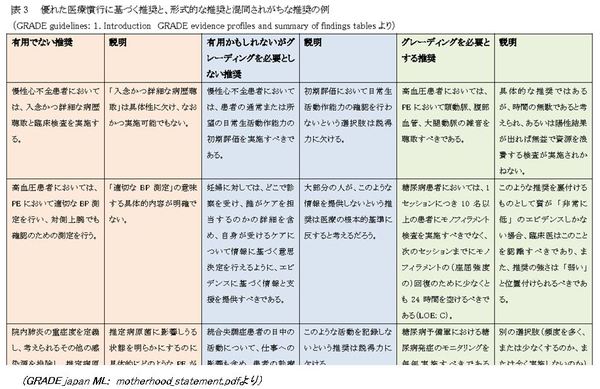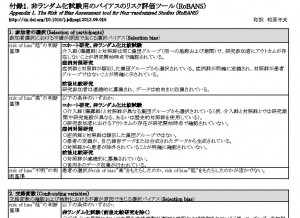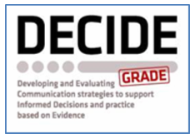Mindsからの報告:
■ 1.『急性胆管炎・胆嚢炎』の医療提供者向け診療ガイドラインを公開しました。(2014/03/18)
◇急性胆管炎・胆嚢炎
‐TG13新基準掲載‐急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン2013
http://minds.jcqhc.or.jp/n/med/4/med0020/G0000565
【編集】 急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン改訂出版委員会
日本腹部救急医学会、日本肝胆膵外科学会、日本胆道学会、日本外科感染症学会、日本医学放射線学会
———————————————————–
やっと、GRADEシステムに関する国内の教科書を引用してくれました。
■診療ガイドラインのためのGRADE システム.
相原守夫,三原華子,村山隆之,相原智之,福田眞作、凸版メディア,弘前,2010.
■アマゾン
本ガイドライン作成グループが適切にGRADEシステムを利用しているのかどうかは、現時点では十分に検討していませんが、評価のプロセスや判断理由は不透明でGRADEに沿ったものではないように思います。いずれ時間があるならば、検討してその結果を以下のサイトで紹介します。
また、本ガイドラインにおいては、新しい試みとして、作成したガイドラインそのものの効果と有用性について記載していますが、検討対象ガイドラインはMinds2007手引きを使ったものです。それでも、「急性胆管炎・胆囊炎診療ガイドラインを遵守した場合、患者の臨床アウトカムが改善し、さらに医療経済的な効果もあるという結論です。