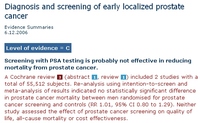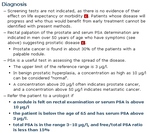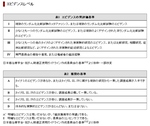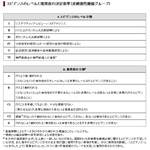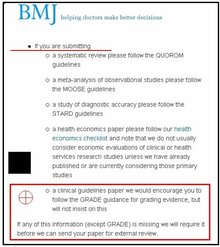革新的な診断技術を用いたこれからの肺がん検診手法の確立に関する研究
主任:鈴木隆一郎(大阪府立成人病センター)
平成18度 第3次がん総合戦略研究事業
■1.本年度の研究成果
本研究は、末梢性肺がんを標的としたCT検診による肺がん検診と、中枢性肺がんを標的とした喀痰細胞診とが、肺がん死亡率の減少をもたらすか否かを検討することを目的としている。本年度の研究結果は以下。
———————————————————————-
● 研究A 2006年2月に官報に掲載された人口動態調査死亡小票に基づいて、7地区の追跡調査が完了した。
CT検診群 47158人の転帰では、死亡1506人(肺がん死亡129人)、平均追跡期間5.4年。一方、通常検診群91971人については、死亡5823人(肺がん死亡402人)、平均追跡期間7.0年であった。
登録時の喫煙状況別に両群の肺がん、全死因粗死亡率を比較すると、どの喫煙状況でも、CT検診群の肺がん・全死因粗死亡率が低い傾向が認められた。
selection biasの影響を軽減するために、喫煙状況別に2群比較すると、通常検診群に対するCT検診群の相対肺がん死亡率(相対全死因死亡率で調整)は、
非喫煙者で 0.62
過去喫煙で 0.85
現在喫煙で 1.06
であり、喫煙の影響が乏しいものほど、CT検診の肺がん死亡率減少効果が大きく、現在喫煙者に対しては、従来型の通常検診と効果に大差ないことが示された。
● 研究B 平成元年の宮城県肺がん検診者からの、喫煙指数600以上の男性10421人のコホートから、喀痰細胞診受診をリスクとするコホート内症例対照研究を実行した。平成4~12年の肺がん死亡例241例、性、年齢、居住区をマッチさせた対照1402例を確定。
胸部X線単独受診を1としたときの症例の確定診断12ヶ月以内の喀痰細胞診受診に関する肺がん死亡オッズ比は、全組織形で1.19(0.83-1.70), 扁平上皮がんで 0.95(0.52-1.73)、であった。
死亡時年齢を75歳以下に限定しても、各々1.15, 0.86(95%CI略)であった。
—————————————————————
■2.研究成果の意義および今後の発展性
(1)喫煙状況別での解析で、非喫煙者で約38%、過去喫煙者で15%、通常検診に比較してCT検診の肺がん死亡リスク減少が示唆されたが、現在喫煙者では両者には差がなかった。CT検診の半数以上が単回受診であるため、進行速度の速いがんの多い現在喫煙者に対しては、CT単回検診が通常検診を上回る効果を検出しえないことを示していると考えられる。
(2)胸部X線に対する喀痰細胞診の上乗せ効果は、症状受診を除外し、症例を75歳以下、扁平上皮がんに限っても約14%の死亡リスク減少が示唆されたにすぎず、有意差はなかった。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[Comments]
CT機器の種類やその他のデータが不明であり(報告は2pのみ)、詳細がわかりましたら追加あるいは修正しますが、CT検診群での肺がん死亡の相対危険は、0.81 (0.67-0.99)程度だろうか。