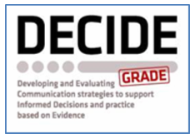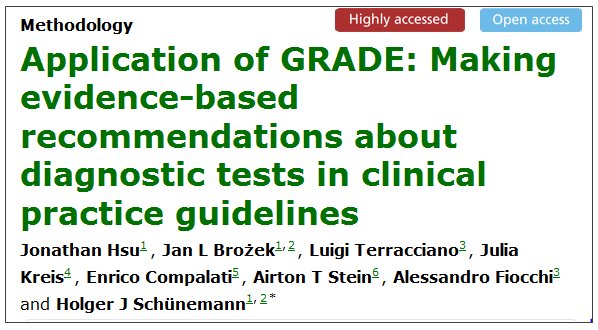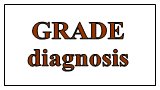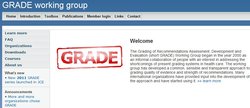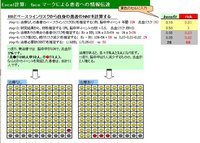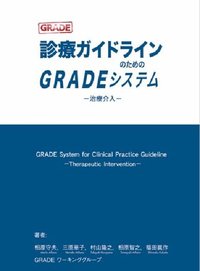DECIDE: Developing and Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practice Based on Evidence
GRADEアプローチを基本として作成したガイドラインを効果的に普及させるため、
DECIDE プロジェクトが、2001年1月よりスタートしています。
DECIDEの一部を翻訳し、計画目的などを以下に紹介します。
——————————————————————–
■DECIDE研究プロジェクトの発足:
DECIDE(Developing and Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practices Based on Evidence): DECIDEは、第7次研究枠組み計画 (Seventh Framework Programme) のもとで推進される、欧州委員会の共同出資による5ヵ年計画 (実施期間: 2011年1月~2015年) である。
■計画目標:
「対象を絞ったガイドライン配布のための方法を開発・評価するために、GRADE Working Groupの取り組みを土台とし、エビデンスに基づく推奨の配布を改善する」
■方法:
GRADEは、エビデンスの質と推奨の強さを評価し伝達するための系統的アプローチである。GRADEは、そもそも他の評価システムの弱点に対処するために開発されたものだが、現在では国際的に広く使用されている。GRADE Working Groupのメンバーにより結成されるDECIDE協会 (DECIDE condortium) は、このアプローチをさらに発展させることで、診療の行方を左右する主な利害関係者 (医療専門家、政策決定者と管理責任者、患者と一般市民) に対し、エビデンスに基づく推奨を効果的に配布することを確実にする。われわれは、諮問グループ、審議、ユーザー調査を通じて利害関係者からのインプットを集める。この取り組みは、欧州の幅広い医療システムにわたって行われる。開発された対象を絞った配布戦略はランダム化試験で評価され、DECIDEパートナーやわれわれが支持する他のガイドライン作成者らにより開発された実際のガイドラインを使用して改良・適用・評価される。
■期待される結果:
多様なセッティングで厳密に評価された推奨配布戦略は、研究の診療への反映を支援し、実際の医療システムに適用される。